##ドル支配の崩壊と資本主義の根本矛盾##
ところでつぎにアメリカの資本輸出――民間直接投資の増大(「多国籍企業」の発展)との関係において、それがアメリカの国際収支にどのような影響をおよぼしているかをみてみなければならない。すでに指摘しておいた点は二つである。一つは、貿易収支の黒字中の縮少ないし赤字への転化を投資収益の増大によってカバーするという、アメリカの国際収支パターンの変化である。いま一つは、六〇年代における民間直接投資の増大が、一方でアメリカの輸出――とくに資本財の輸出――増加を支えてきた反面、他方では「多国籍企業」の現地における生産活動が拡大し、それとともに現地販売や第三国市場への「多国籍企業」の輸出が増大しはじめるのに照応して、それはアメリカの輸出市場を圧迫しひいては国際収支を圧迫しはじめているということであった。
そこでまず、六〇年代におけるアメリカの民間直接投資の増大についてみてみよう。アメリカの民間長期投資の年平均投資規模は、五〇年代半ばの一八億ドルから六〇年代初期には三三億ドルへ、さらに六〇年代末期には七二億ドルに増大してきた。(注6)そのうちの七割以上が直接投資であり、証券投資との比重は六〇年代をとおして七対三の割合で推移している。(注7)このアメリカの直接投資は主要国(アメリカ、イギリス、EEC、日本)の直接投資総額のうち一貫して七〇%近くを占めている。(注8)
また従来――戦前から一九五〇年代まで――はカナダとラテンアメリカに半分以上向けられていたアメリカの民間直接投資は六〇年代には対ヨーロッパ向けの投資が増大している。それはまた直接投資の対象とする産業分野の変化に対応しており、第二次大戦前の直接投資が植民地後進国における石油・鉱山開発を中心としていたのにたいして戦後は製造業を中心に直接投資が伸びているのが特徴である。アメリカの場合でみると、石油・鉱山業と製造業の割合は、五〇年代にはそれぞれ四七%と三七%であったのが、六〇年代には三〇%と四六%へ逆転している(注9)しかもその製造業への直接投資のうち半分以上がヨーロッパ向けであり、一九七三年の製造業海外子会社の新規工場・設備支出のうち五二・六%がヨーロッパ向けであった。(注10)
さらに製造業投資のなかでも中心は重化学工業であり、アメリカの在ヨーロッパ製造業子会社への資本の純流出は、六二年~六九年で化学、輸送機械、機械など重化学工業向けが七三%を占めた。(注11)こうして在ヨーロッパアメリカ系子会社の設備がヨーロッパ諸国の製造業設備投資総額に占める比率は六〇年代に急上昇し、生産に占めるシェアも大きな比車を占めるにいたっている。たとえば自動車ではアメリカ子会社の生産シェアはイギリスで五〇~五九%、EECは二四%、石油精製業でのシェアはイギリスで三〇~三九%、ドイツで三五%に達している。(注12)
さらに戦後開発された先端技術商船については、アメリカ系子会社の生産シェアは一層高く集積回路では九五%、半導体とコンピューターでそれぞれ八〇%に達している。(注13)
このような「多国籍企業」の海外生産活動は当然貿易を含む世界経済全体に、なんらかの影響をもたらさずにはおかない。通常、直接投資残高とそれにもとづく生産との間には一対二の関係があるといわれている。そのような推計にたったある計算によると一九六六年の先進国直接投資残高九〇〇億ドルにもとづく生産額は一八〇〇億ドルに達し、これは同年の先進国の輸出一四〇億ドルをこえ、資本主義世界全体の輸出一八〇〇億ドルと同じ額になる。(注14)
ところでアメリカの民間直接投資の増大が一面で、アメリカの輸出を増大させてきたことについてはすでに指摘したが、実際「多国籍企業」の関与する輸出はアメリカの輸出総額のなかでかなりの比重を占めている。一九六六年にアメリカの輸出総額のなかでそれは四六・九%、七〇年には五〇・六%におよんでいる。(注15)またその輸出の伸び率も全輸出のそれをしのいでおり、六六~七〇年に金輸出の伸びは四三・三%であったが、「多国籍企業」関連輸出の伸びは五四・七%に達した。(注16)とくに戦後の資本輸出がすでにみてきたように機能資本としての直接投資の増大であったことと関連して資本財の輪出を促進してきたことは疑いない。
だが他面では、製造業部門の直接投資残高の増加は海外生産活動の比重を高めるとともに、それにくらべての輸出の地位の相対的低下を招いている。海外子会社の生産物はたんに現地で販売されるだけでなく、逆にアメリカ本国へ輸出され、また第三国へも輸出されアメリカ本国からの輸出品と市場を奪い合うことになる。一九六八年には海外子会社の販売総額のうち七七・八%が現地で販売されたが、約八%はアメリ力本国へ輸出され一四%強が第三国へ輸出された。(注17)いま表六および図Ⅱでみても、海外子会社を含むアメリカ企業(製造業)の対外販売高に占める輸出の割合は低下している。とくに一般機械、輸送機械、化学のシェアの低下が著しい。製造業全体でみても一九五七~七〇年で四一・二%から二七・六%に低下している。
第七表 アメリカの直接投資の国際収支に与えた影響(試算)(単位 百万ドル)
| 65年 | 70年 | |
| (1) 輸出に及ぼした影響 輸出置換による輸出の減少 子会社向輸出 (2) 輸入に及ぼした影響 逆輸入による輸入増加 (1)+(2) 貿易収支に及ぼす影響 |
|
|
| (3) 投資収益の増加 (4) ロイヤリティ等の増加 (3)+(4) 貿易外収支に及ぼした影響 |
299 |
696 |
| (5) 純資本流出 | △ 1,525 | △ 1,328 |
| (1)+(2)+(3)+(4)+(5) 国際収支に及ぼした影響 |
△ 4,135 |
△ 9,021 |
1.60年以降アメリカからの新規の直接投資がすべて抑制され、子会社の投資収益の再投資および現地資本調達による投資のみが行なわれたと仮定した。
2.影響はアメリカからの新規資本流出分についてみたものである。
3.逆輸入による輸入増加には国内生産代替不可能なものは含まない。
4.計算方法について付表2参照(資料) Survey of Current Business, G.C.Hufbaur & F.M.Adler "Overseas Manufacturing Investment and the Balance of Payment" 1968 U. S. Treasury Dept. を用いて試算。
(通商白書 1972, p. 144)
すでにみたように、「多国籍企業」の現地販売高の増加がアメリカ本国からの輸出を圧迫し、国際収支を悪化させている無視しえない要因になりつつある。たしかに海外子会社から送金される利潤や技術収入などの投資収益は年々増大し、六〇年代はほとんどの年も資本流出額よりも投資収益のほうが上回っている。民間投資収益は六〇~六四年平均三九億ドルから七〇年には六二億ドルにも増大している。
この点で、アメリカの国際収支のパターンは貿易収支の黒字中の減少を、投資収益の厖大な黒字によってカバーする寄生性と腐朽性を強めた帝国主義国のそれである。だがそれでもなお、「多国籍企業」の現地生産によるアメリカの輸出の減少をカバーしているわけではない。表七は、「六〇年代の直接投資がアメリカの国際収支にどのような影響を与えたかを、ハフバウァー、アドラーの輸出置換の算定式」によって算出されたものである。これによると、「六〇年代の直接投資はそれがなかった場合と比較して、七〇年代では、海外投資に基づく利益送金は資本流出額よりも大きくなっているものの、全体としては、九〇億ドル国際収支を悪化させていると推定される。この悪化の大部分は対外投資の輸出代替効果(現地生産によるアメリカの輸出の減少)による」(注18)ということである。
このように戦後の資本輸出がつくり出した「多国籍企業」の発展は生産の国際化を途方もない規模で推し進め、従来の資本主義的国民経済を基礎とした枠組みの外に、いわばもう一つの――第三の――経済活動領域を形成しつつあるかのようである。ただし注意しておかなければならないのは、当然のことであるが、多国籍的な展開をとげているのは資本の生産活動、すなわち剰余価値生産とその実現が多国籍的規模で行われているというだけであって、資本所有が多国籍化されているわけではない、ということである。しかしそれにもかかわらず「多国籍企業」による国際的な資本の集中は極度に進んでいるのであり、一国民経済の統制の枠をこえた生産活動と資金の移動――とくに国際短期資金の移動――が展開されていることも事実である。そしてまた「多国籍企業」の国境の枠をこえた生産活動は、国民経済の枠でとらえる“国民総生産”や“国際収支”には反映されないどころか逆に攪乱的作用をおよぼしているといってよい。また「多国籍企業」と結びついて形成発展し拡大している“ユーロ・ダラー市場”の国際短期資金の移動は、一国の金融政策の統制を離れてますます無政府性を強めており、昨今の国際通貨危機に投機的ケイレン的性格をもたらすうえで最も重要な攪乱的要因をなしている。さらに、この国民経済的規制の枠から離れた第三の経済的活動領域の拡大が、アメリカ帝国主義の世界経済に対する支配の崩壊と対応していることは、極度に社会化された生産と所有の私的性格との矛盾という、まさに資本主義の根本的矛盾の、資本主義の歴史的崩壊局面における現象形態といえないであろうか。
##世界経済の危機と抬頭する保護主義の今日的性格##
いずれにせよ、以上みてきたように六〇年代に入ってからアメリカの全体としての輸出競争力は低下し貿易収支の黒字中は六〇年代後半になると著しく縮少していった。それにもかかわらず、対労働者国家圏と対植民地革命との関係における、いいかえれば「世界的二重権力構造」によって余儀なくされる支出を過大な規模でつづけざるをえない。まさにそのことによって六〇年代一杯をとおしてドル危機は進行してきたのである。
| このドル危機の克服にむけてケネディ、ジョンソンのもとで種々のドル防衛策がとられたが、ほとんど何の効果ももたらさなかった。五〇年代から六〇年初頭にかけてアイゼンハワーのもとで軍事支出の削減が試みられ、海外軍事支出は、二九億ドルから二三・七億ドルへ五・三億ドル削減された。しかし新植民地後進諸国の経済危機のために政府贈与・借款はかえって増大し、政府の対外支出全体は五八―六〇年の年平均五三・三億ドルから、六一~六四年に平均五一・五億ドルにわずかに減少したにすぎない。ところが、アメリカにおける投資環境の悪化と利潤率の低下を背景に、通貨の交換性を回復し共同市場を発足させたヨーロッパにむけて、民間資本の流出が増大した。民間資本の純流出額は五八~六〇年の二六・五億ドルから、六一~六四年には平均四三・三億ドルに増加した。 これに対してケネディは、①対外支出の削減、②民間資本流出の阻止、③輸出拡大と対米差別貿易の撤廃要求、等を中心にしたドル防衛策を展開した。だが対外政府支出はほとんど削減することができなかったし、民間資本の流出も減少するどころかむしろ激増していった。たしかに六〇年代前半は、国際競争力強化のための国内経済強化策によって、自動車、住宅を中心に一定程度の拡大をとげることができたし、五八、九年にくらべて輸出も伸び貿易収支も改善された。しかしアメリカの輸出に対する差別の打破とEECの関税障壁の突破による市場拡大のもくろみは、イギリスの加盟交渉の失敗によって崩れてしまった。また関税引下げ交渉をめぐるケネディラウンドは六二年末に交渉が開始されながら最終的に妥結をみたのは一九六七年であった。こうして六四年末には、アメリカの対外短期債務二三〇億ドルにたいして、金保有高はわずかに一五四億ドルという状態になっていた。 かくして、六五年ジョンソン大統領によって四度目のドル防衛策が打ち出されるが、ベトナム反革命戦争への介入となによりもベトナム革命の勝利的前進そのものによって、ジョンソンのドル防衛策はみじんに打ちくだかれ、ドル危機は決定的破局の局面をむかえたのであった。 ところで何度も指摘してきたように、世界貿易におけるドルの流通回路はアメリカの非商業的ドル支出によって完結させられていた。ということは、ドル支配を経済的に支える構造が労働者国家と植民地人民に対する「世界反革軍事体制」という政治的構造であった、という奇妙な――というより第二次大戦後の世界経済に本質的な特徴――関係にあった。したがってアジアを中心とする反革命体制を維持しきることなしには、ドルの流通回路そのものが攪乱され麻痺させられたのである。 ケネディのドル防衛策が、植民地革命の進展に対する反革命的介入のための軍事戦略をこの時期展開せざるをえなかったことと結びついていたのは、まさにドル支配の本質を示すものといってよい。(この点については―「第四インターナショナル」誌№26「アメリカのポストベトナム世界軍事戦略」―神崎論文―参照) この点と関連して若干指摘しておかねばならないのは次の点である。六〇年代のドル危機はヨーロッパに対するアメリカからの金の流出の激増によって端的に現象したわけであるが、アメリカのEECを中心とした対ヨーロッパ国際収支は黒字であった。それにもかかわらずアメリカはヨーロッパ諸国に対して年平均一二億ドルないし一四億ドルの金・ドルを支払ったのである。これは「要するに、アメリカの対西欧国際収支は黒字であるにもかかわらず、第三地域へのアメリカのドル流出が回り回って西ヨーロッパ諸国へのドル流入となり、これがアメリカの対西欧黒字を上回り、アメリカは西欧諸国に対し巨額のドルを支払うことになったのである。(注)ということであった。 |
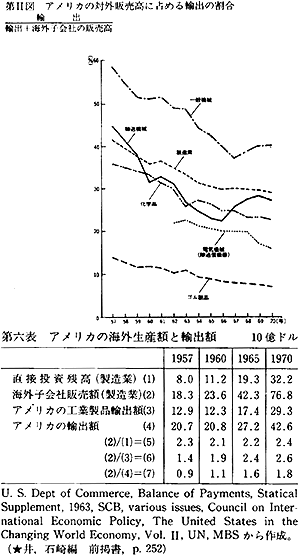 |
かくしてドル危機を決定的にしたのはベトナム革命の勝利的前進にほかならなかった。
「だがアメリカ帝国主義のベトナムへの介入は、朝鮮戦争のときとその事情が全く異っていた。朝鮮戦争のときはアメリカ帝国主義はなお絶対的な経済的優位を保っていたし、全体として経済成長率もまだ低落傾向を示してはいなかった。このようななかで、朝鮮戦争は、四八~四九年の一時的不況局面からの脱皮をもたらした。軍需の急速な拡大が経済に与えた影響は、アメリカ経済の成長をもたらすとともに、世界経済全体の急速な拡大をもたらしたのである。
ところが六五年以降のベトナムは、ケネディ大統領のもとで六三年以来おしすすめられてきた赤字財政と信用膨張をテコにした経済政策によってインフレが強まっていた時期であった。しかも全体としてのアメリカの経済力は下降しはじめている段階であった。そのうえ一九六四年には金準備が一五四億ドルと公的流動債務と同額にまで減少し、ドル危機は決定的な転機に直面していた。
またこのベトナム・エスカレーションは、アメリカにおける急速なインフレの進行をもたらした。卸売物価は六〇~六五年の一・五%に対して、六五~六八年の間に平均三・三%、約二倍の上昇率を示し、さらに六九年に四・七、七〇年に五・一とその上昇テンポは急速に加速化していった。このインフレの昂進は、アメリカの輸出競争力を低下させ、自動車をはじめとする工業製品の輸入増加をまねいた。その結果貿易収支の黒字中は急速に減少し、六四年の六六億ドルが、六七年に三八億ドル、六八、六九年には七~一○億ドル程度に急速に減少していった。ところが六五年以降、対外軍事支出は大巾に増え、六四年の二九億ドルが、六六年三八億ドル、六八年四六億ドルにまで増加した。この国際収支の大巾な赤字にともなって、金準備も急速に減り、ついに一九六八年のドル危機によって、ドルは事実上金との交換を停止(金プール制の廃止と金の二重価格制)せざるをえないところにまで追いこまれたのである。ベトナム革命の勝利的前進は、確実にアメリカ帝国主義の支配を解体させていったのである。
これ以後、七一年のニクソン声明によってバルは名実ともに金との交換を停止され、さらに同年末のスミソニアン合意をとおして、ドルの切下げが迫られ、危機はますます深刻さを増していった。ところが金の裏づけを失ってもなお、ドルは基軸通貨としての役割をになわなければならなかったし、国際収支の赤字をとおして流出しつづけたのである。この過剰ドルの流出テンポは七一年になっていちだんと加速化した。それは貿易収支がはじめて赤字(二九億ドル)になったのを反映して、一挙に二一九億ドル (七〇年は三八億ルの赤字)もの巨額の赤字を記録したのである。これによって世界的なインフレはますます加速化されていった。ヨーロッパ諸国はもはやドルのこれ以上の流入によるインフレの昂進を許容しえなくなった。ドルを支えるために自国の経済を犠牲にすることを拒否しはじめたのである。」(「第四インターナショナル」誌№10「IMF体制の崩壊」五七~五八頁より)
以上みてきたように、戦後の世界経済は重化学工業化を基礎にした高度成長の過程で水平分業を発展させることによって一面では工業諸国間の相互依存を強めてきたが、反面では先進工業諸国の産業構造の同質化を推しすすめてきたのである。まさにこの構造と矛盾のうえでドル支配の崩壊がすすんだのであり、今日の輸入制限競争の激化と保護主義の抬頭が進行しているのである。
そして今日の保護主義は、一九世紀的な「幼稚産業」の保護でも、二〇世紀初頭の「独占保護関税」でもなく、まさに高度成長をけん引してきたが、すでに競争力を失いはじめた重化学工業部門の基幹的大規模産業を中心とした「保護」政策なのである。これは資本主義の根本的危機のもとで、過剰生産恐慌の矛盾が貿易面において表面化したもの以外のなにものでもない。まず第一に先進工業諸国の産業構造が同質化されてきていることによって、個々の商品輸出や産業分野をめぐる貿易摩擦や衝突ではなく、今日の貿易摩擦と不均衡の背景にあるのは、産業構造の同質化した性格そのものの衝突なのである。第二に水平分業の進展をとおして相互依存を深めてきたということは、いいかえれば貿易面をとおしても生産の国際化を推しすすめてきたということ、すなわち生産に占める輸出の割合が極度に大きくなっているということである。たとえば日本の自動車産業はこの間、生産量のほぼ五〇%以上を輸出向けに生産している。そして図Ⅲにもみるように先進工業諸国の生産活動はますます多く輸出にむけられていくのである。
そしてアメリカでもこの間、輸出競争力の低下してきた中位技術分野の重工業製品である鉄鋼、自動車、家電製品などについて輸入規制倍置を強めている。また日本の製品別輸出依存度をみても(表八)、同種の重工業製品の輸出依存度が急速に高まっているのである。
さらに日本の場合こうした状況のなかで、長期の不況から脱出するにあたっても輸出に依存する度合が大きくなってきている。景気のボトムから一年間について輸出のGNPに対する増加寄与率を過去と比べてみると、一九六五年の不況期が一五・八%、一九七一年不況のそれが一六・一%に対して、今回は二七・五%に達している。(注19)
このように日本経済はとくに対外依存度を著しく増大させてきたぶんだけ、世界経済の危機のなかでより大きな困難と破局に直面することになる。しかも、今日の世界経済の構造のもとでは、“危機”を無政府的に“輸出”することができない。前進する“世界革命”と対峙しつつ没落と崩壊の淵を転げ落ちる資本主義的世界経済は、アメリカ帝国主義の経済的・政治的力量の枠内で、その統制に屈服せざるをえない。
第8表 主要商品の輸入依存率、輸出率
|
|
|
|
|
|
|
綿糸 合成繊維糸 人絹糸 綿織物 人絹織物 毛織物 織機 普通自動車 自転車 ミシン テレビ受像機 普通鋼圧延鋼材 陶磁器 セメント 船舶 硫安 写真機 |
|
||||
|
2.0 |
1.3 |
2.1 |
2.2 |
1.5 |
|
アメリカ帝国主義は、原子力を含むエネルギーと食糧、そして世界にはりめぐらした軍事網を武器に、危機のなかで分解しつつある世界経済を統制するためのイニシアチブを再確立しようとしている。
かくして、世界経済の危機は、ますます各国内部の政治危機としてはねかえり、深められていかざるをえない。
以上述べてきたように、世界資本主義の危機はこれまで世界経済をリードしてきた諸国の間で輸入制限競争を激化させ、保護主義的傾向を増大させている。七七年六月のロンドン会議にむけて、カーターは米・西独・日は世界経済をけん引する“三台の機関車”たるべきたと提唱した。だが事態は逆に、三極構造のあいだの摩擦の激化を浮彫りにした。とくに今日日米通商交渉にひきつづく、ECの厳しい対日要求の押しつけ、といった形で日本に対する攻撃が集中している。
そこで日本の対EC、対米貿易の構造的特徴についてみておく必要がある。まず、ここ十年来、対米貿易、対ECともに一貫して日本の黒字であり、その黒字中は石油危機直後の例外を除いて年々拡大してきている。とくに七六、七七年は対米、対ECとも日本の黒字が極端に増大し、対日批判を強める結果になった。
ところで日・米貿易構造の特徴をみると、アメリカの対日輸出の主要商品は食糧、飲料原材料と機械類であり、そのうち一次産品が約七〇%をしめている。逆に日本の対米輸出の主要商品は鉄鋼、輸送用機械、一般機械で工業製品がほとんど一〇〇%このような構造のもとでは、アメリカの景気上昇局面ではつねに日本の大中な輸出超過となる。というのはアメリカの対日輸出品は、所得弾力性(GNPが一上昇するのにともなう輸入比率)が小さな一次産品が大半を占めるため景気の動向にはあまり影響されない。これにたいして日本の対米輸出品は所得弾力性の大きい耐久消費財中心の工業製品がほとんどでありアメリカの景気上昇によって大巾に伸びる傾向をもっている。
日・米間のこの貿易構造はよくいわれるように一見“相互補完的”で問題かないようにみえるけれども、それはアメリカの“在来産業”の輸出競争力の低下と日本の種々の輸入制限によってつくり出されたものであり、今日まさにこのような貿易構造そのものが問題にされ、貿易摩擦の原因となっているのである。そもそもアメリカの商品別輸出構造をみると、現在の対日貿易のパターンにみるように、けっして一次産品が七〇%を占めるという構造ではなく、逆にやはり工業製品が輸出全体の七〇%を占めている。いいかえれば、アメリカの側からすれば日米貿易構造はこれまでの“相互補完的”なパターンから“競合的”なパターンへ転換させようとするだろう。というより日本に対して工業製品の輸入拡大を迫るという形をとるし、実際そのような要求が出されてきている。
こうしたなかですでにみたように、アメリカは鉄鋼、自動車、家電製品といった、競争力の低下した中位技術分野の“在来産業”製品にたいして輸入制限を強化しつつ、知識集約度の高い航空機、電算機、医療機器といった分野の市場拡大を求めてきている。
ところが日本の場合は、この間まさに鉄鋼、自動車、家電製品が一貫して輸出品の花形であったし、いまもなお輸出の大半を占めている。日本の輸出における重工業化率は、六五年の六二%、七〇年の七二%から七五年には八三%にまで上昇し、さらにこの工業製品総輸出の中で上記の
“中位技術分野”の商品が七五年で四七・四%と約半分を占めている。
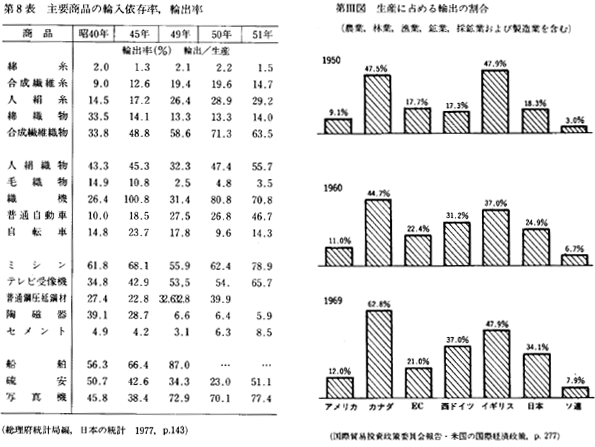 |
したがってこの分野の輸出がさまざまの輸入制限措置によって抑えられることは、日本経済にとって重大な打撃となる。そのうえ、日本経済はいままさに知識集約化・省資源化へむけて産業構造を高度化していかなければならない局面にあり、この点でもアメリカの要求と鋭く衝突している。
また対EC貿易についてみても、日本の対EC輸出はほとんど十割かた工業製品で占められ、ECの対日輸出も九〇%は工業製品でありこの点で日本――EC間の貿易構造は同質的な競合型をなしている。そして輸出数量の点では、工業製品の場合、日米間のそれは三対一の割合で日本の圧倒的輸出超過であり、対EC間でも二対一の割合で日本の出超である。
この点、米――EC間についてみると、ECの対米輸出はその九〇%が工業品であるが相互に一対一の割合でいわば相殺し合っている。したがって米――EC間貿易についてはその分をこえる一次産所の輸出によってアメリカの黒字になっている。
つまり、総体的に賀易依件度の小さいアメリカや、城内貿易の比重の大きいEC諸国と比べて、日本の場合は必然的に貿易摩擦をひき起こすような構造をもっていることがわかる。日本の場合は輸出構造そのものが、特定商品を特定地域にむけて集中豪雨的に輸出するパターンをとっているといってよい。これは輸出の重工業化率が八〇%を超えているといったことや、相対的に貿易依存度が高いうえにとくに対米市場への依存度が大きいといったことから明らかである。
いいかえれば、この間日本経済の対外依存度が大きくなっていた分だけ、今回の「円高」を契機とする米、ECの日本に対する集中攻撃は、それだけ日本経済に対する一層大きな打撃を意味するといってよい。
七八年度予算はある意味でこの日本経済の危機の深さを表現している。そこで最後に七八年度予算の性格と日本経済の危機について若干ふれておかなければならない。
七八年度予算の編成は、当初は「財政再建」をめざす“緊縮型”をめざそうとしていた。それが、“円高”の圧力と後半以降の“ミニリセッション”〔小さな景気後退〕のなかで超大型の景気刺激型予算に組み替えられていった。このような経過そのものが非常に不安定な、日本経済の構造的危機を表現している。と同時にその内容は、明白に“安定成長型”財政の破綻を示している。「第二次補正予算」を含む“一五ヵ月予算”という形で、“財政再建”どころか逆に会計年度の枠を無視したところで予算を組まざるをえなくなっている。そのうえ“国債依存度”も三〇%の枠を大きく突破し、税収の先食いを除いた(七八年度予算の収入は七九年度四・五月の税収をも先取りしている)実質ベースでは三七・八%で約四割近くに達しようとしている。これは昭和七~九年の水準と肩を並べる赤字財政である。“円高”がもたらした危機のなかでより大きな財政危機に見舞われながら、その矛盾を先のばししたび縫策に貫かれているのが、七八年度予算の基本的性格である。
それは来年度以降のより一層すさまじい大衆収奪を組み込んだ予算編成となっている。
注1 大島清編「戦後世界の経済過程」東大出版一一二頁
注2 同上
注3 同上 五五頁
注4 同上 五六頁
注5 楊井克己・石崎昭彦編「現代世界経済論」東大出版三六頁
注6 同上 二二二頁
注7 野村昭夫著「世界経済と多国籍企業」五六頁
注8 「現代世界経済編」二二五頁
注9 同上 二三一頁
注10 「世界経済と多国籍企業」六二頁
注11 「現代世界経済論」二三六頁
注12 同上 二三七頁
注13 同上 二三七~八頁
注14 同上 二五一頁
注15 「世界経済と多国籍企業」一二六頁
注16 同上 一二七頁
注17 同上 一〇〇頁
注18 通商白書一九七二年版一四二頁
注19 「興銀調査」一九〇号五頁