第三章 日本資本主義の蓄積構造とインフレ体質
##一、インフレ促進的金融構造と水脹れ##
以上みてきたような国家と大資本の驚くほどの結合のもとで、日本のブルジョア経済は極めて急激な高度成長をとげてきた。
経済の実質成長率は、一九五〇年代以来一貫して、平均一〇%を上回ってきた。GNPは、五〇年の一〇九億ドル(資本主義世界第七位)、五五年に二四〇億ドル(六位)、六〇年には四三〇億ドル(五位)、そして七〇年には二〇〇〇億ドルをこえて、第二位にのし上った。五年間にほぼ二倍、十年間には四倍近い強成長をとげたのである!
この間産業構造の上では、極度の重化学工業化がすすみ、重化学工業化率は、六〇年の四九%に対して、七〇年には六〇・七%に達し、製造業に占める重化学工業生産額の比率は七五%を占めるにいたった。
こうして六〇年代半ば以降、重化学工業を中心に、世界市場への輸出攻勢が展開された。工業製品の輸出総額は、六〇年の三六億ドル、六五年の七八億ドルから、七一年には二二〇億ドルに飛躍的な増加をみせている。
そのうち重化学工業品は毎年二五~三〇%近い増加率(三、四年毎に倍増)を示し、七一年には総輸出のほぼ七五%を占めるにいたっている。そして世界貿易に占める割合も五〇年の一・五%から七〇年に六%を上回っている。
ところが同時に、この高度成長の時期をとおして、消費者物価は一貫して上昇しつづけた。だが大企業にとっては、この物価の上昇こそ強蓄積のための温床であった。
というのは、欧米資本主義の内部留保にもとづく直接金融方式と異なり、日本資本主義は間接金融方式(=外部資金倍入れ)によってその膨大な設備投資をまかなってきた。企業はその資金調達を外部からの倍入れによってまかなうということは、力量以上の資本投下を保障するだけでなく、ひきつづく物価上昇、就中地価の高騰のもとで、借入れ利得さえ生み出し、資本の調達を一層有利にしてきたのである。さらに国家による財政、金融上のあらゆる優遇措置と保護が、この間接金融方式を助成するように働いてきた点は、すでにみてきたとおりである。
このために日本の企業は、アメリカやヨーロッパに比べて自己資本比率が非常に低い。
アメリ力やヨーロッパの場合六〇%以上なのに、日本の企業は、全産業でみて、六○年に三〇%だったが、六五年に二四・一%、七○年には一九・三%と低下の一途をたどってきた。つまり設備投資の七〇~八○%以上を外部資金にたよってきた。
このために、企業の資金調達は、膨大な大衆収奪に基礎をおく政府の銀行の手に大きく依存する構造がつくりあげられた。云いかえれば、政府と銀行から大企業にむけた集中的融資が大規模に行われてきたということである。
たとえば、五九~六四年の全産業法人の金融機関借入れ増加額のうち、資本金十億円以上の企業(五九年表企業数で〇・四%)の増加が六七・三%、長期借入れ金では七三・二%を占めていた。
こうして大企業は、自己の資本蓄積力をはるかに上回る巨大な投資を、銀行からの過剰な借入れによってまかなってきた。それとともに、大企業はこの銀行からの借入れ金によって土地を買い占め、それによって地価の暴騰をつくり出し、その土地投資がもたらす含み益が企業の担保能力を高め、さらに借入金の調達を容易にしていくという、このカラクリをフルに利用したのである。五五年から七二年までGNPは八倍弱に対して、資本金二百万以上の全法人企業からの土地は、帳簿価額残高が、なんと八〇・四倍である。しかもこれは、ほとんど脱税に近いわずかな税負担しかもたらさないような、一平方メートル五六八円というべらぼうに安い帳簿価格にもとづいて計算してなお、このありさまなのである。いま、七一年度末の東京証券市場一部、二部上場一、三〇〇社についてみると、その所有土地の、帳簿上の価格二兆八、九五八億円が、時価六一兆七、三〇七億で、含み益五八兆、三四九億円になるという。しかもそれ以後の地価の暴騰分や、系列子会社を通じて保有している土地については計算に入っていないのであるから、実際には「この数字はさらに膨大なものになる。そして、「最近の四、五年間で民間企業が取得した土地は、全国で四〇万ヘクタールをこえ、全国土地面積の一%に達している」(新全総の総点検、『土地問題に関する中間報告』)といわれている。
かくして、五五年以降の地価高騰の推進力は、大企業の設備投資競争そのものにあったことは明白である。しかし、この含み益はあくまで計算上の利益であるために、企業の借入れ金の増大は、経営における損益分岐点を高める。つまり、固定費化したともいえる巨額の金利を支払うために、企業は操業度を一定水準以下に引き下げることができないのである。
かくして、大企業への融資集中――技術革新にもとづく設備投資競争の激化――高操業度の維持というパターンが、ひとつの産業肥大症として定着してきた。このようなパターンで急激な強蓄積をなしとげてきた日本資本主義は、その過程ではじめから水脹れ的な過剰な資金を抱えこんで回転してきたのである。
それがフル回転しているあいだは、その水脹れした資金も、生産のより一層の拡大によって吸収されていく。ところがひとたび、フル回転してきた生産拡大基調が停滞しはじめると、水脹れした資金が生産の拡大に吸収されなくなり、過剰生産の矛盾が不可避的に、すさまじいインフレの高進を生み出すことになるのである。そして、「管理通貨制」にもとづく戦後資本主義は、本質的に、過剰生産の矛盾をインフレに転化する構造の上に成立してきたのである。
##二、高度成長と労働者人民の貧困の累積##
だが資本の蓄積はプロレタリアートの貧困の蓄積である。しかも、すでにみてきたような大衆収奪的構造をもって遂行された高度成長の裏面史は、膨大な農漁民の切捨てを含む棄民の累積以外のなにものでもなかった。農漁民の全就業者中に占める比率は、五○年の四四・六%から、六〇年に三七・七%に、七〇年には一八・一一%にまで急速に低下した。しかもその圧倒的部分が、兼業化=半プロレタリア化したのであって、農漁民中の専業者の比率は、五〇年の三六・一%から六〇年に一九・二%、そして七〇年にはわずか五・二%と、さらに急激な減少を示している。
ということは、重化学工業化を軸とした高度成長の過程で、農漁村の破壊といわゆる中間層のプロレタリア化が、驚くべき規模と速さですすめられたということである。この過程で労働者数は総体として増大(五〇年の三八・七%から七〇年に六二%)するのは当然であるが、注目しなければならないのは、婦人労働者の急速な増加である。その数は、五〇年の三〇〇万人から、六〇年に六四六万人へ、さらに七〇年には一、一二〇万人へと、十年間にほぼ二倍づつ増加したのである。全体で占める比率は、二五・七%から三〇・三%へ、そして三四%へとその比重を高めて来た。そしてこのインフレの中で主婦の就業が不可避となり、パートタイマー等を含めると、すでに男子労働者を上回ったという! しかもその婦人労者の七割近くが家庭の主婦だといわれている。
そしてこのパート・タイマーというのは、その大部分が午前九時から午後四時までの勤務時間と二万円以下(!)の低賃金で、地方に進出した大企業の“分室”が下請工場の不可欠の労働力として完全にビルトインされているのである。
「四〇才代の婦人が進出する造船溶接職場、三一~五二才の主婦ばかりの時計部品工場、農家の主婦がコンピューターの配線束ねをする工場“分室”、自動車関係の縫製業を請負う農協の工場……」等々。
このように急速な就業構造の変化が、恐るべき都市の過密と結びついて、日本列島のすべての労働者人民の耐え難い精神的・肉体的緊張と消耗の度合を強めていることは疑いもない事実である。
なるほど高度成長の時期をとおして、賃金は一定程度上昇した。だが労働生産性の上昇は、年率九%であるのに、賃金コストは年率二・八%の割りで低下している。六五年から七〇年まで、前者が一四・五%も上昇しているのに対して、後者はわずか〇・二%の上昇にとどまった。
従って労働分配率は極端に低く、六〇年代後半で、アメリカの五一%、イギリスの五三%に比べ、日本は三二・三%である。
しかも日本の場合、低賃金の差別的な重層構造が、極めて複雑巧妙な形でできあがっており、これこそが日本資本主義の強蓄積をその底辺から支えてきたのであった。
まず周知のように、規模別の賃金格差が非常に大きな開きをもって構造化されている。
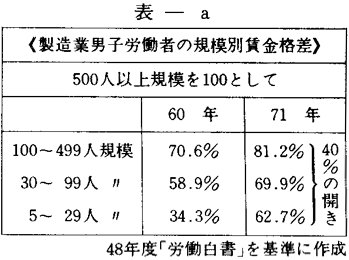 |
その実態を現実の給与額でみると、七〇年における毎月の定期給与で、五〇〇人以上規模の場合六万九八二円、一〇〇,四九九人規模では、五万八四六円と一万円の格差があり、三〇~九九人規模では、四万六、四八八円と一万五千円近い格差を示している。これはあくまでも政府統計による総平均であって、圧倒的多くの労働者の実態はさらにひどい低賃金と格差の開きをもっているだろう。とくに婦人労働者の場合は、平均男子賃金のほぼ半分である。(六〇年に四二・八%が七二年に五〇・二%) さらにこの規模的格差のうえに、下請、孫請制度と重なる準社員、作業員、見習工、季節=臨時工、パート・タイマーといった、より一層複雑な差別的階層序列が重なり合うのである。一例をあげれば、「新日鉄の下請工(三六)は、基準内賃金四万五、〇〇〇円弱に三万七、〇〇〇円強つけ加えるために、四〇・五時間の残業、三四時間の深夜業、二二時間の休日出勤をする。また別の労働者(三〇)は、基準内賃金三万三、〇〇○強に約三万を加えるために、六〇・五時間の残業、八五時間の深夜業、八時間の休日出勤に耐えている」という状態である。 |
高度成長期における巨大な設備投資と、スクラップ・アンド・ビルドによる省力化がすすみ、新鋭一貫工場におけるコンピューターと結合した自動化と連続化がすすむなかで、労働はますます単調な反復作業にとって代り、ますますチャッブリンのモダンタイムズに似たものになっている。
一例をあげれば、「石柚化学などのようなシステム化された装置工業の計器監視工などの監視・記録、“正常値”からのずれの修正……」、しかも相つぐコンビナートの爆発によって暴露されたごとく、災害を回避するしくみさえもたず、「労働者の強度の緊張によって安全が保たれているような作業工程(鉄道幹線の交通労働などにもこれと同じ)」、自動車のエンジン組立てラインで「一台のエンジンが通過する時間は二分」だという。電器工場などでは、「ラジオのプリント基板に部品のとりつけやハンダ付けをする一回七〇秒の仕事」、また電々公社の電話交換手のもとにも「コールが二秒ごとに自動的にブレストに入るシステム」が導入されている。
そこでの労働は、すべて一回の作業が数十秒から数分の単位で、一日何千回、何万回とくり返される単調な機械的労働の反復である。そしてこの高速化されたラインについているのは、ほとんどが中・高卒の低賃金労働者であり、さらに季節工やパート・タイマーが導入されているのである。さらにまた、この高速化された新鋭設備の周辺に必要とされる「激しく、つらく、危険で汚い作業」はすべて下請け化される。下請工の作業は、大別すれば「荷役、運送、機械の整備、梱包、建築、スクラップ処理、清掃、雑役」であるという。
| 鉱石ヤードに揚げた鉱石をダンプで運ぶ。怒濤の如く鉱石を流し出すベルトコンベアを整備し、その下に溜まる粉鉱石をスコップで清掃する。高炉に、鉱石、コークス、石灰を食わせる。転炉からあふれる銅鐸をブルドーザーで押す熱い仕事。これらすべての危険で汚い重労働が、高温と一二〇ホンを越す轟音の中で行われているという。 そして重化学工業部門の大企業において、こうした下請化の傾向はますます大きくなっている。新日鉄の場合で五七年(八幡)に、本工三万七、六三〇万人、下請・社外工二万一、四八〇人であったのが、いまでは表-bのように下請工が大巾に増加している。とくに新しい工場ほど下請化率が高いということは、高度成長下の技術革新の進行とともに、下請化がすすんでいることを物語っている。この他に、毎日印鑑をもらって入る日雇労働者や労働下宿などの日雇・臨時社外工が一日に七~八千といわれる。そしてこのほとんどは、下請会社といっても、大企業のために労働力を確保するだけのトンネル会社なのである。 このような状態のなかで、相つぐコンビナートの爆発の犠牲者、労働災害による死傷者は、圧倒的に下請工であり、季節工である。 労働災害による死傷者についてみると罹災者総数は、毎年三十万~四十万以上であり、そのうち毎年五千人~六千人以上が殺されていっている。そして六三年(昭和三八年)から七二年(四七年)のまさに高度成長の十年間の累計をみると、罹災者の数は三八七万三、一六七人であり、死亡者は六万一、五〇七人である! 表-cに労働災害による死傷者数の推移を示した。 |
 |
|
表-d 新日鉄における昭和45年度
|
そして、新日鉄の例で七〇年の死亡事故を本工と下請工についてみると表-dのとおりであり、彼らの勤続日数は、ほとんどが一日から一三日、ないし二〇日だという。ほとんどなんの知識も与えられないままに、極めて危険な仕事に就労させられている実態が一目瞭然である。 またこうした労働災害は、「四組三交替制」が実施された七○年四月以降から急激に増えたという。鉄鋼労働者の調査によると、七○年の本工労働者の死亡事故は六五名、下請労働者一八八名、計二五三名で、六五年の各五七名、一二五名、一八三名に比べて四〇%の増加である。 もはや高度成長と資本の強蓄積が、労働者にとって何を意味したかは明白である。 それに、工場排水による海洋汚染や大気汚染が、農民・漁民・地域住民にもたらした死傷災害を、さらにはるかに上回る規模で襲いかかってきているのである。 |
##三、高度成長の循環的側面と輸出主導型への転換##
以上みてきたような構造――国家によって行われる大規模な大衆収奪に依拠した資本調達と国家の財政・金融構造と一体化した資本蓄積機構、企業内部における差別的雇用構造に基礎を置いた強搾取、そして公害防止設備などの一切のマイナスの投資を省き、その犠牲のすべてを労働者と農・漁民・地域住民に転嫁しつづけてきた構造――のもとで、急激な高度成長をとげてきた日本資本主義が明らかにいまひとつの破局にぶつかっている。今日のすさまじいインフレの高進――とくにスタグフレーションと呼ばれる不況下の異常な物価騰貴――は、この十数年にわたる高度成長の過程で蓄積してきた矛盾が、一挙に、集中的に表面化してきているものである。それは、資本主義が本質的に避けることのできない「過剰生産恐慌」の戦後的形態にほかならない。もちろんそれはかつての「恐慌」のように短期的パニックとしてはあらわれていない。
しかし、新規採用のとりやめや、合理化による首切りが失業率を高めていくなかで、ブルジョア経済さえマヒさせるほどのインフレの高進による大衆収奪の一層の強化が進行している。戦後資本主義の構造は、一貫して「恐慌」の危険を、このようななしくずし的な形で、労働者人民の犠牲に転嫁しつづけてきたのである。
全体として、戦後資本主義の急速な成長は、二〇世紀の初期の段階や一九三〇年代と比較して、「客観的に資本主義的生産関係をより一層侵略した」のである。今日世界的規模で同時的に進行しているスタグフレーションは、資本主義の発展がその生産関係の上限に達したころで直面している危機と困惑の形態にほかならない。
とくに脆弱な基盤の上で急激な高蓄積をなしとげてきた日本資本主義は、いったん均衡を失うや、そのギャップの巨大さの分だけ増中された危機に見舞われるのである。
つまり、これまで高度成長を支え、促進してきたすべての諸条件とメカニズムが、それ自身の弁証法によって、すべて危険を促進し増中する要因に転化するのである。
そこで、今日、日本経済が直面している危険の性格をより一層鮮明にするために、高度成長の過程を簡単に循環的側面からふりかえってみよう。
五〇年代から六〇年代前半までの段階では、傾斜生産方式による国家の援助をともなって、電力・鉄鋼・石油など基礎条件をつくられた家電・自動車・合繊などの耐久消費財関連の重化学工業が飛躍的に発展し、それがさらに、鉄道・港湾・道路などの公共投資とも結びついて、再び基礎生産の投資を誘発していった。こうして内需に依存しつつ「投資が投資を呼ぶ」民間主導型の成長パターンの中で、急速な重化学工業化を達成したのである。もちろんこの高度成長の過程は、単調な上昇カーブを描いているわけではなく、五八年、六五年と景気後退を経てきている。だがこれは古典的な意味での景気循環を示しているのではなく、IMF体制を軸とした、いわゆる「管理通貨制」のもとでの、フィスカルボリシー〔金融政策〕による景気調整にほかならない。
まさしくそれによって、設備過剰の矛盾が累積するのを政策的に調整し、より一層の大衆収奪へとその矛盾を転嫁していったのである。
六五年以前の日本の国際収支の基調は、経常収支の赤字を、資本収支の黒字でカバーするという型をとってきた。とくに五五年以降は、それまで経常収支の黒字をまかなってきたアメリカからの経済援助と朝鮮戦争による特需は大巾に減少し、輸入面において、工業用原材料資源が圧倒的比重を占め、さらに技術革新にともなう特許権使用料などの資本負担経費の赤字中が急速に増加した。
それに比して、輸出構造においては、まだ軽工業――中小企業製品が高い比重を占め、貿易収支の赤字構造がつづいていた。まさにこのことのうちに、内需中心といっても、それが消費中心ではなく、投資中心であり、かつまた中小企業が輸出で稼いだドルで、重化学工業用の原材料を輸入するという、大資本偏重の特質をみてとることができる。
このような構造のもとで、成長が急激であればあるほど輸入が急増し、それかたちまち国際収支悪化――政府の金融引締め――不況というプロセスをふんで景気調整が行われていったのである。しかしこれこそ、脆弱な経済体質のうえで、急速な重化学工業化をとげていく際の摩擦を、労働者人民の犠牲(多くの中小企業の倒産と首切り、インフレ)に転嫁していく過程にほかならなかった。
しかもそれは財政・金融をテコとした、国家の全面的な介入によって行われたのであり、それを可能にしたのがIMF体制化の固定レート制にほかならない。
かくして景気調整の過程でも、国内均衡を犠牲にして国際収支の均衡を保ち、資本投下リズムと規模を、損失の最も少い形で調整していくという、大衆収奪側面はフルに作用したのである。そしてまさに第二章でみたような国家と資本の強固に癒着した蓄積機構が、このような循環を描きつつ膨れ上っていったのである。
なるほど、ドル支配が安定し成長余力が充分大きかった間は、IMF体制下の固定レートのもとで、財政・金融面からする金融引締め=景気調整は実に効果的に(大衆収奪の効果が!)働いたのである。
だが六四~六五年のいわゆる「構造的不況」を転機として、日本経済は内需中心の成長パターンから、輸出主導型のパターンに変っていった。そしてこの時期以来、日本資本主義はそれ自身の構造的矛盾を外に輸出し、戦後のドル支配の基礎を掘り崩していくとともに、逆に、世界恐慌と世界政治がもたらす危機と矛盾をより一層ストレートにこうむる構造の中に、ますます深く組み込まれていくことになるのである。
まず六四年半ばから進行していった不況は、それ以前といくつかの点で異った特徴を示した。六四年末から、需給のアンバランス=生産過剰の目立ってゆくなかで、鉄鋼・家電・合繊等が、あいついで不況カルテルや、通産省の行政指導による操短を開始した。この時期六五~六六年一月まで認可された不況カルテルは、一八品種という戦後最大の件数にのぼった。さらに中小企業の倒産、信用不安が激しく、中小企業の倒産件数は、六三年の三、一一八件から、六四年には、四、九三一件に、さらに六五年には、六、〇六〇件に増加した。また、それ以前の不況時には、並行的に低下傾向した消費者物価が下らずに、逆に大巾に上昇した。そしてとくにこの時期の不況の性格を特徴づけたのは、それまでの労働力過剰から、労働力不足への転換という構造的変化の中で、大巾な設備投資の累積による未償却資産の比率の増大、金利負担の上昇といった資本コストの上昇を、労賃の減少によってカバーできなくなり、企業利潤の低下――投資削減へとつながっていったことである。明らかに、内需中心に推移してきた高度成長が一定の生産過剰を抱えこみはじめたのである。
従って、この不況からの回復の過程では、国際収支が輸出の伸びによって大巾に改善したにもかかわらず、また、四〇年の一、四、六月の三回にわたる金融緩和にもかかわらず利潤動機の低下から、生産の回復はかなりの遅れを示したのである。
結局、蔵相福田の登場と国債の発行による財政需要の創出をきっかけに、輸出の拡大に領導された設備投資の再然という形で景気が回復していったのである。ところで、この輸出の拡大は、けっして単純なものではなく、アメリカのベトナム反革命戦争のエスカレートと、ドルのタレ流しが生んだ「ベトナム特需」をテコにしたものであった。アジア市場向けの輸出の増大は、反共諸国家へのアメリカの特需によるドル撒布に支えられたものであったし、アメリカ向け輸出の増大は、ベトナム景気の持続とアメリカ国内におけるインフレの高進に支えられたものであった。
だがいずれにせよ輸出は三〇%増と増え、この時期以降国際収支は好転し、それまでの経常収支赤字・資本収支黒字というパターンから、経常収支の黒字によって資本収支の赤字を埋め合わせていくというパターンに変化した。
そしてまた前回の不況局面からの回復の際には、輸入の改善寄与率が九六%であったのにくらべてこの時期は、輸出増の寄与率が八〇%であったことをみても、輸出の増加が果した役割は決定的であった。
しかも、輸出増加の七割が重化学工業製品を軸にしたものであり、その結果輸出構成においても、重化学工業品の比重が前年五四%から六五年五七%へさらに上昇した。これにくらべて軽工業製品は前年の三九%から三六%に低下しー伝統的な輸出品である繊維品の割合は二三%から二一・四%に低下した。
このように日本資本主義は、明らかに重化学工業品のウエイトを高めつつ、輸出偏重型のパターンへ移行していったのである。とくに第三章でふれたように、日本の大企業は外部資本に依存した資本調達構造をもつため、金利負担の増大が損益分岐点を高め、そのことが高操業度の維持を強制する体質をもっている。かくして、この段階から除除に過剰生産の矛盾を抱えこみはじめた日本資本主義が、その本質的に産業肥大症的な構造のうえに、強力な輸出ドライブをかけていかなければならなかった必然性が明日である。
そしてもちろん、ここでも税制・金融面からする国家の輸出優遇策が強力に働いた。
なるほどたしかに、重化学部門を軸とする大企業の労働生産性は、飛躍的に強化され、「規模の経済」に基礎を置く巨大な独占企業が育ってきた。そして国家によって充分に保護されつつ、その競争力の強化された製品を海外にむけて売りさばいていったのである。だがその場合ですら、日本の大企業は、新たなダンピング的二重価格制度によって、輸出市場におけるシェアの拡大をはかっていったのである。つまり、輸出価格を極度に低く抑え、そのしわ寄せをすべて国内価格に転嫁する方式である。その際の価格の設定の仕方は、「……いわゆる平均生産費を基準とするのではなく、国内価格には設備投資の負担・償却をあてこんだ高い価格をそして輸出価格には、変動費(材料費、外圧加工費、運賃など)を基準とする安い価格……」によって決定されてきた。(注④)
そして国内価格は、独占的市場支配と「旧式工場における高コスト=高価格の存在に依拠」し、輸出価格は、技術革新と「規模の経済」を達成した輸出競争力の強化を背景に、「世界の代表的新鋭工場の生産コストを基準にして設定」されてきたといわれている。(注⑤)
ここでは、明らかに他の先進工業国に比較した低賃金のみならず、国内消費者の収奪によって、低い輸出価格の成立がはかられていることがわかる。たとえば「19型コンソール・カラーテレビの場合、工場・原価を一〇〇として、対米輸出価格一三四・八に対して、国内価格四一二・五と三倍以上であり、一五〇〇?の乗用車で、同じく対米輸出価格一二〇に対して、国内価格二・三倍といったぐあいである。」(注⑥)このようなメカニズムが働いているなかで、六〇年代を通じた高成長期をとおして、消費者物価が一貫して上りつづけたのに、卸売物価が比較的安定していたということは、そのしわ寄せがいかに直接的消費者に転嫁されつづけてきたかということを如実に示している。
このように、独占企業による国内市場の支配と再販価格制度などをとおした保護によって、いかに大きな大衆収奪が、日本資本主義の高度成長を支えてきたかを知ることができる。そしてまたここでもインフレ要因を蓄積していくことになるのである。
かくして六五年以降大企業合併があいつぎ、競争力の強化を背景とした、海外、とくにアジアへの進出が猛裂な勢いで展開されたのである。
実際、六五年の日産・プリンスの合併、六五年の三井造船による藤永田造船の吸収、六八年の川崎系三社の合併、そして六九年の富士・八幡の合併による新日鉄の誕生と、重化学部門における寡占体制は急速にすすんだのである。そしてこのような寡占体制の強化が、独占的市場支配と管理価格をもたらし、大きなインフレ要因となってきたことは、今日の事態が明白に示している。このようにして、日本の大企業は、急速に対外競争力を強化した。六五年の通産省調べによって、一九の主要工業生産物の生産水準をみると、レーヨン、アセテート短繊維、商業車で第一位。綿花、非セルロース系繊維、新聞用紙、合成ゴム、硫酸、プラスチックおよび合成樹脂、セメント、銑鉄、粗鋼、アルミニウム、精銅、亜鉛の十二品目が米国についで二位。わずか四品目だけが三位以下だったという。
こうした競争力の強化を背景に、最近では商品輸出だけでなく資本進出がめざましい勢いですすんでいる。とくに日本の大企業の海外進出は政府援助にたすけられつつ、そのほとんどがタイ、韓国、台湾、インドネシア、南ベトナムといった軍事独裁下の、ほとんど日常的に反対党が圧殺されている反共諸国家にむけられている。しかもそこにおける賃金は、低賃金の日本のさらに二分の一、三分の一という低賃金で、台湾などでは、日本円に換算して、わずか五~六千円の低賃金労働者がいまだに(七〇年)一五%もいるといわれている。ドル危機と国際通貨体制の動揺、世界市場をめぐる競争の激化の中で、過剰資本をかかえた日本のブルジョアジーが、今後ますます激烈な形で海外進出をはかっていくしかないことは明白である。実際、自動車、ミシン、テレビ等まで含めて、多くの企業がノックダウン方式の進出をすすめているのである。だが、周知のようにチリ、インドネシア、韓国でいま、「日貨排せき」運動が新たな高揚を示している。